この記事を書いた人
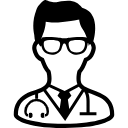
日本糖尿病学会専門医、日本内科学会認定医の資格を持ち、医師として約18年医療現場に立つ。
特に糖尿病の分野に力をいれており、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症などの慢性代謝疾患の診療を得意としている。2026年5月に美濃加茂市でクリニックを開業予定。
「血糖値スパイク」とは、食後1~2時間の短い間に血糖値が急激に上昇する現象を指します。
空腹時血糖やHbA1cが正常範囲内でも起こり得るため、隠れ糖尿病予備軍や糖尿病として見逃されやすいのが特徴です。
目次
なぜ血糖値スパイクが問題なのか
空腹時血糖やHbA1cが正常範囲内なら問題ないのでは?と思われる方もいらっしゃるでしょう。
ですが血糖値スパイクが起こると、身体に以下のような悪影響が出ます。
動脈硬化の進行
急激な血糖値の上昇は血管内皮細胞にダメージを与え、炎症や酸化ストレスを引き起こします。これが蓄積すると動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めます。
インスリン分泌への負担
一時的でも高血糖になると、そのぶんインスリンを大量に分泌しなければなりません。繰り返すことで膵臓のβ細胞が疲弊し、将来的なインスリン分泌低下につながります。
低血糖リスク
血糖値が急上昇すると、その後インスリン過剰分泌で急激に血糖値が下降することがあり、めまいや動悸、倦怠感を感じる場合があります。
認知機能への影響
急激な血糖変動は脳にもストレスを与え、長期的には認知機能低下や認知症リスクの増加と関連すると指摘されています。
発見しにくい
通常の健康診断では空腹時血糖のみを調べることが多く、血糖値スパイクを見つけることができません。そのため対処が遅れる可能性があります。
血糖値スパイクが起きやすい人
日常生活の中で、以下に心当たりがある方は血糖値スパイクが起こっている可能性があります。
- 早食い・大食いの習慣がある
- 炭水化物中心の食事をしている
- 朝食を抜くなど食事リズムが不規則
- 運動不足やストレス過多
特にダイエットや間食制限で朝食を抜く方は、午後の血糖コントロールに影響しやすいため要注意です。
血糖値スパイクの見つけ方
経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)
血糖値の変動を把握する検査で、糖尿病の診断に用いられます。75gのブドウ糖が入った溶液を服用し、飲む前、飲んでから30分後、60分後、120分後にそれぞれ採血して糖尿病かどうかを判定します。ブドウ糖液を飲んだ後の血糖値が急上昇する方は、日常生活で血糖値スパイクを起こしている可能性があります。
持続血糖モニタリング(CGM)
皮下に小さなセンサーを装着し、1〜5分ごとの血糖変動をグラフで可視化。気づきにくい血糖値の急上昇が一目瞭然になります。
食後の体調チェック
食後の強い眠気、だるさ、集中力低下、イライラなどは血糖スパイクのサインかもしれません。
食事でできる改善策
急激な血糖値上昇は、糖質の摂取をゆるやかにする工夫で抑えることができます。
以下のようなことを実践していくことが大切です。
食べる順番を変える
まず野菜(食物繊維)→たんぱく質→炭水化物 の順に食べることで、血糖値の上昇がゆるやかになります。
ゆっくり噛む
一口あたり20~30回噛むことで唾液の消化酵素が働き血糖値の上昇を抑えます。
食事回数を分ける
一度に大量に食べず、1日3食を基本に必要なら軽い間食を入れて血糖値の山を小さくする。
低GI食品を選ぶ
玄米、全粒粉パン、野菜・海藻・きのこ類など、GI値の低い食材を中心に。
間食の工夫
どうしても甘いものがほしいときは、ナッツ、チーズ、ゆで卵、プレーンヨーグルトなど低糖質でたんぱく質を含むものを摂取するようにしましょう。
運動による対策
運動は血糖値スパイク対策に有効です。
エスカレーターを使わずに階段を使う、帰宅時にはひと駅分歩いてみるなど、少しの積み重ねが大きな対策に繋がります。
食後の軽い運動
10~15分の散歩やストレッチで筋肉に糖が取り込まれやすくなります。
定期的な有酸素運動
週150分程度のウォーキングや水泳でインスリン感受性を改善。
筋力トレーニング
筋肉量を増やすと、糖の消費量がアップし食後の血糖値の上昇を抑えやすくなります。
必要に応じた薬物療法
血糖値スパイクの治療に使うお薬は色んな種類があります。
患者さんの状態に合わせて医師が判断いたします。
α-グルコシダーゼ阻害薬
炭水化物の分解を遅らせ、食後血糖の急上昇を抑制。
グリニド薬
食事直前に服用し、インスリン分泌を即座に促進して食後高血糖を防ぐ。
DPP-4阻害薬/GLP-1受容体作動薬
食後のインクレチン効果を高め、血糖ピークを穏やかにする。
薬剤はそれぞれ特長が異なるため、生活パターンや合併症リスクに応じて使い分けます。
血糖値スパイクが気になる方はご相談ください
血糖値スパイクを放置すると、知らず知らずのうちに血管ダメージを蓄積し、重大な合併症へとつながる恐れがあります。
日々の食事と運動でコントロールしつつ、必要なら薬の力も借りて、血糖値の山を平坦にすることが大切です。
当クリニックでは、OGTTやCGMによる実態把握から、食事・運動指導、薬物療法まで一貫したサポートをご提供します。血糖の波を穏やかにして、健康な未来を一緒に築きましょう。