この記事を書いた人
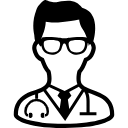
日本糖尿病学会専門医、日本内科学会認定医の資格を持ち、医師として約18年医療現場に立つ。
特に糖尿病の分野に力をいれており、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症などの慢性代謝疾患の診療を得意としている。2026年5月に美濃加茂市でクリニックを開業予定。
糖尿病において見逃せないのが、「食後血糖値の急上昇(血糖スパイク)」です。
近年では、HbA1cが高くない人でも、食後だけ異常に血糖値が上がることが血管障害の原因になると注目されています。
この「食後高血糖」に対して、食べ物が糖になる過程をブロックしてコントロールする薬が「αグルコシダーゼ阻害薬(α-GI)」です。腸で作用し、糖の吸収を穏やかにするという、非常にユニークで効果的なアプローチの薬です。
目次
αグルコシダーゼ阻害薬とは?
私たちが食事で摂取する炭水化物(糖質)は、小腸で「糖」に分解されて吸収され、血液中の血糖値を上昇させます。
この「分解の鍵」を握る酵素がαグルコシダーゼです。
α-GI薬はこの酵素の働きをブロックし、糖の分解と吸収をゆるやかにすることで、食後の血糖上昇を抑える作用があります。
主なα-GI薬と特徴
| 一般名 | 商品名 | 特徴 |
| アカルボース | グルコバイ | 作用が強く、便通への影響が出やすいことも |
| ボグリボース | ベイスン | 腸への負担が少なく、高齢者にも使いやすい |
| ミグリトール | セイブル | 単糖にも効果あり、食後血糖抑制が明確 |
すべて食事ごとに服用する薬で、1日3回、毎食直前に飲む必要があります。
α-GI薬のメリット
食後血糖の急上昇を防げる
糖質の吸収をゆるやかにすることで、血糖値スパイクの予防に役立ちます。
膵臓に負担をかけない
インスリン分泌を促す薬ではないため、膵機能が低下していても使用可能です。
低血糖リスクが非常に少ない
単剤ではほぼ低血糖を起こさず、安全性が高い薬として知られています。
食生活の改善効果を補助できる
糖質が多い食事や外食が続きやすい方でも、ダメージをやわらげる手段として有効です。
注意点と副作用
腸管への副作用(ガス、膨満感、下痢など)
糖質の分解・吸収が遅れることで、腸内細菌による発酵が進みガスが発生します。特に以下のような方は腹部の張りや不快感を感じやすくなります。
- 野菜不足の方
- 食物繊維が少ない食生活
- 運動不足
そのような場合は、「少量から開始して慣らす」「食物繊維を意識した食事にする」「発酵性の強い食品を控える」などの対処をして不快感を和らげることができます。
薬の飲み忘れによる効果減退
毎食直前の服用が必要なため、飲み忘れると効果がなくなるのが難点です。
食前にセットで携帯できるケースなどでの工夫が必要です。
他薬との併用について
α-GI薬は、ほぼすべての糖尿病薬と併用が可能です。特に以下のような組み合わせで相乗効果が期待できます。
- インスリンやSU薬と併用する場合は、低血糖リスクがやや上昇(もし低血糖をおこした場合、砂糖ではα-GI薬の作用により吸収が遅くなってしまうため、ブドウ糖を速やかに服用する必要があります。)
- DPP-4阻害薬やSGLT2阻害薬と併用すれば食後血糖+空腹時血糖の両面にアプローチ
「血糖値はそこそこ…でも調子が悪い」方へ
HbA1cがそれほど高くなくても、「なんとなく疲れやすい」「午後になると眠気が強い」「食後にぼーっとする」などの症状がある方は、食後の血糖スパイクが原因の可能性があります。
α-GI薬は、食事の「吸収スピード」に介入する唯一の薬です。
症状やライフスタイルに合わせて使えば、体調改善と合併症予防の両方に効果的です。
まずはご相談ください
α-GI薬は、糖尿病治療薬の中でも「入り口でコントロールする」非常にユニークな薬です。食後の高血糖を穏やかにすることは、血管を守り、合併症リスクを減らすためにとても重要です。
当院では、血糖値だけでなく「食後の体調」「日々の生活習慣」「食事の傾向」も重視しながら治療を提案しています。
「血糖値はそこまで悪くないけど、何か不調がある」
そんな方こそ、ぜひ一度ご相談ください。あなたに合った薬と生活改善のバランスをご提案いたします。