この記事を書いた人
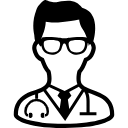
日本糖尿病学会専門医、日本内科学会認定医の資格を持ち、医師として約18年医療現場に立つ。
特に糖尿病の分野に力をいれており、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症などの慢性代謝疾患の診療を得意としている。2026年5月に美濃加茂市でクリニックを開業予定。
糖尿病は、日々の生活習慣と密接に関わる病気です。なかでも「食事」は、血糖コントロールに最も大きな影響を与える重要な要素のひとつです。薬や運動も大切ですが、糖尿病の治療において基本となるのが食事療法です。
しかし、「どんな食事をすればいいの?」「全部制限しなければいけないの?」と不安になる方も多いでしょう。このコラムでは、糖尿病の食事療法について詳しく解説し、今日から取り入れられるポイントをお伝えします。
目次
糖尿病と食事の関係
糖尿病とは、血液中のブドウ糖(血糖)が慢性的に高くなる病気です。その最大の原因は、インスリン(血糖を下げるホルモン)の働きの異常。食事で糖質を摂取すると血糖値が上がりますが、糖尿病ではこの調整がうまくできず、高血糖の状態が続きます。
食事療法の目的は以下のとおりです。
- 血糖値を適正に保つ
- 体重や脂質、血圧を整える
- 糖尿病合併症のリスクを下げる
- 薬物療法の効果を高める
つまり、糖尿病治療における食事は“制限”というより“体を整えるための方法”と捉えていただいた方が自然です。
糖尿病の食事療法|5つの基本原則
摂取カロリーを自分に合った量に
1日のエネルギー摂取量は、年齢・体格・日常活動量により異なります。基礎代謝や運動量をもとに、医師や管理栄養士が個別に目標カロリーを設定します。
たとえば、体重60kgで身体活動量が「普通」の方の場合、1日の適正カロリーはおよそ1,800~2,000kcal程度が目安です。
「食べすぎていないつもり」でも、間食や飲み物で過剰カロリーを摂ってしまっていることも少なくありません。
栄養バランスを意識した食事
血糖値に影響を与えるのは糖質だけではありません。たんぱく質・脂質・食物繊維などをバランスよく摂取することが重要です。
- 主食:ごはん、パン、麺類(適量)
- 主菜:肉、魚、卵、大豆製品
- 副菜:野菜、きのこ、海藻類
これらをバランスよく組み合わせる「一汁三菜」の形が理想です。
食物繊維をしっかり摂る
野菜や海藻、きのこに含まれる食物繊維は、糖の吸収を穏やかにする働きがあり、血糖値の急上昇を防いでくれます。
目安としては1日20g以上の食物繊維を摂取することが推奨されています。
食事のタイミングと回数
食事を抜くと次の食事で血糖値が急上昇しやすくなります。1日3回、決まった時間に食事を摂ることが血糖管理には重要です。
また、夜遅くの食事や寝る直前の食事も血糖値に悪影響を与えるため、避けましょう。
よく噛んでゆっくり食べる
食事に時間をかけ、ゆっくり噛んで食べることで、満腹感が得られやすくなり、血糖値の上昇も緩やかになります。
続けるコツとサポート体制
食事療法は、無理をしすぎず、続けられる工夫をすることが大切です。
- 目標を数字だけにせず、「体が軽くなった」「眠りが良くなった」など生活の変化を楽しむ
- 家族の協力を得る
- レシピに飽きたら栄養士に相談して新しいメニューを取り入れる
まずはできることから始めましょう
糖尿病の食事療法は、「我慢する」ためのものではありません。自分の体を知り、コントロールするための前向きな方法です。完璧を目指さず、一歩ずつ自分のペースで改善していくことが成功の鍵です。
「食べすぎてしまう」「何から始めればいいかわからない」そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。当院は、あなたの糖尿病治療のパートナーとして、全力でサポートいたします。