この記事を書いた人
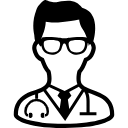
日本糖尿病学会専門医、日本内科学会認定医の資格を持ち、医師として約18年医療現場に立つ。
特に糖尿病の分野に力をいれており、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症などの慢性代謝疾患の診療を得意としている。2026年5月に美濃加茂市でクリニックを開業予定。
目次
糖尿病性腎症とは?
糖尿病性腎症とは、血糖値の上昇によって腎臓の機能が低下してしまう合併症です。
腎臓は“沈黙の臓器”とも呼ばれ、自覚症状がないままじわじわとダメージが進行するため、知らないうちに人工透析が必要な状態に至ることも少なくありません。人工透析は日常生活への影響が大きいため、今のうちから予防に努めましょう。
腎臓ってどんな働きをしているの?
腎臓とは、血液中の老廃物を尿に変えて排出する器官で、血管が集まった糸玉のような塊(糸球体)になっています。これが体内の老廃物をろ過する「フィルター」の役割を持ちます。
しかし糖尿病になると腎臓でのろ過機能がうまくいかなくなります。
微量アルブミン検査を用いると、ごく初期の変化から見つけることが可能となります。
多くの場合、一度進行するとなかなか元に戻すことは難しい病気でもありますので、早めに見つけ治療することが大切となります。
健康診断で腎臓機能の異常が出たら注意しましょう。
糖尿病性腎症とは?
腎臓は、血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として排出する臓器です。このろ過を行う「糸球体」と呼ばれる部分は、非常に細かい血管のかたまりで、高血糖状態が続くことでダメージを受けやすくなります。
糖尿病性腎症では、この糸球体が次第に硬くなり、尿にタンパク質が漏れ出す「蛋白尿」が現れ、やがて腎機能そのものが低下していきます。
病期の進行と特徴
糖尿病腎症は、主に以下の5段階で進行します
| 病期 | 状態の概要 | 検査所見 |
|---|---|---|
| 第1期(前期) | 自覚症状なし | 正常アルブミン尿 |
| 第2期(早期) | 自覚症状なし | 持続する微量アルブミン尿 |
| 第3期(顕性腎症期) | むくみや高血圧が出る | 蛋白尿が陽性に |
| 第4期(腎不全期) | 尿毒症状が出始める | eGFRが30未満に低下 |
| 第5期(透析療法期) | 透析が必要 | 腎機能がほぼ消失 |
特に注意したいのが、第1〜2期は完全に無症状であり、健康診断で「腎機能に問題なし」と言われている間にも病状が進行している可能性があることです。
健診で見逃してはいけないサイン
以下の項目が高い・低いと指摘されたことはありませんか?
- 尿タンパク陽性
- 尿中アルブミン:30mg/gCr以上
- eGFR:60未満
- クレアチニン値が高め
これらはいずれも「腎機能の黄色信号」を意味します。血糖値ばかりに目が行きがちですが、腎臓の働きがすでに低下し始めている可能性もあるのです。
なぜ腎症は恐ろしいのか?
透析が必要になる
一度腎不全になると、週3回の透析治療(1回4〜5時間)が一生続くことになります。生活の自由が大きく制限され、身体的・精神的負担も大きくなります。
心疾患や脳卒中のリスク増加
腎臓の機能低下は、血圧や動脈硬化にも影響し、**心筋梗塞・脳梗塞のリスクが2〜3倍になるといわれています。
見た目には現れにくい
むくみ・倦怠感・尿の変化などが現れたときには、すでに進行期であることが多く、元に戻すことが困難になります。
治療と予防の基本
血糖コントロール
最も重要なのは、血糖値の安定化です。HbA1cを7.0%未満に保ち、急激な血糖変動を避けることで腎臓へのダメージを減らすことができます。
血圧管理
高血圧は腎機能を悪化させる大きな要因です。糖尿病性腎症がある方は、収縮期血圧130mmHg未満が推奨されています。
塩分制限
食塩摂取は1日6g未満が理想とされ、薄味を習慣化することが予防のカギです。
タンパク制限
病期によっては、タンパク質摂取量の調整も必要になります。栄養バランスを考慮し、医師・管理栄養士の指導を受けながら取り組みましょう。
当院の取り組み
当クリニックでは、以下のような体制で糖尿病腎症の早期発見と予防に努めています
- 定期的な尿検査・血液検査(eGFR・Cr・尿中アルブミン)
- 食事療法の個別指導(栄養士との面談)
- 腎臓専門医との連携(必要時紹介)
- 患者様ごとの“目標値”設定によるオーダーメイド治療
「まだ症状が出ていない今だからこそできる対策」を重視し、生活習慣の改善から治療薬の調整まで一貫してサポートしています。
よくあるご相談 Q&A
はい。糖尿病をお持ちであれば、腎機能がすでに低下している可能性があります。軽度の変化でも一度チェックを受けましょう。
いいえ。適切なタイミングで準備を進めれば、透析後も充実した生活を送ることは可能です。ただし、透析を回避できる段階での対応が最も大切です。
はい。糖尿病性腎症は「無症状で進行する」のが特徴です。だからこそ、**数値と定期検査が最良の防御策**になります。
腎臓を守るために、今できることから
- 毎年の健康診断を活用する
- 血糖・血圧・塩分のコントロールを意識する
- 尿検査を定期的に受ける
- 医師とよく相談し、自分に合った目標設定を行う
糖尿病性腎症は、早期に気づき・行動することさえできれば防げる合併症です。
「見えない危険」に備えましょう。ご相談はお気軽に
当クリニックでは、糖尿病性腎症のリスクを少しでも感じた方に、検査から予防指導までワンストップで対応しています。
「健診で気になることがあった」「最近むくみやすい」「糖尿病が長く続いていて心配」——そんな方は、今すぐご相談ください。あなたの“沈黙の臓器”を守るお手伝いを、私たちがいたします。