この記事を書いた人
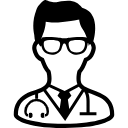
日本糖尿病学会専門医、日本内科学会認定医の資格を持ち、医師として約18年医療現場に立つ。
特に糖尿病の分野に力をいれており、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症などの慢性代謝疾患の診療を得意としている。2026年5月に美濃加茂市でクリニックを開業予定。
糖尿病治療薬は数多くありますが、その中でも世界中で最も多く使われている薬が「メトホルミン」に代表されるビグアナイド薬です。
「インスリンを出させる薬」ではなく、「インスリンが効きやすい体を作る薬」として、2型糖尿病の基礎を支える、まさに“王道”の薬です。
体重、脂質、動脈硬化リスクなど、糖尿病に付随する生活習慣病全体の改善にもつながる多面的な効果が期待されており、長期治療の土台としても活用されています。
目次
メトホルミンとは?
メトホルミンは、主に以下の3つの作用によって血糖値を下げます:
- 肝臓から糖が作られるのを抑える(糖新生抑制)
- 筋肉や脂肪細胞でのインスリンの効きを良くする(感受性改善)
- 腸からの糖の吸収を遅らせる
つまり、インスリンの“出”ではなく“効き”を良くする薬であり、膵臓に負担をかけずに血糖値を安定させることができます。
メトホルミンのメリット
低血糖のリスクが少ない
メトホルミンは、血糖値が高いときだけ自然に作用するため、単独使用ではほとんど低血糖を起こしません。
体重が増えにくい
他の血糖降下薬に比べて、体重が増える副作用が少なく、むしろ体重減少が期待できるケースもあります。
脂質や動脈硬化への好影響
- 中性脂肪やLDLコレステロールを下げる
- 動脈硬化の進行を抑える
- 心筋梗塞・脳卒中リスクの低下に関与する可能性も
経済的にも優れている
後発医薬品(ジェネリック)も広く流通しており、治療コストを抑えながら長期的に使えることも大きな利点です。
こんな方におすすめ
- 初期の2型糖尿病と診断された方
- インスリン抵抗性が強く、生活習慣に課題がある方
- 肥満傾向があり、治療に際して体重を増加させたくない方
- コレステロール・中性脂肪が高い方
- 他の薬で効果が不十分な方の追加療法として
特に、若年発症の2型糖尿病患者さんや、生活習慣の影響が大きい方には、最初の選択肢としてメトホルミンが使われることが非常に多いです。
使用時の注意点と副作用
主な副作用:胃腸症状
- 吐き気、胃のムカムカ感、腹痛、下痢など
- 特に飲み始め1〜2週間に出やすい
対処法としては以下が考えられます。
- 少量から開始して徐々に増量(漸増療法)
乳酸アシドーシス(非常にまれだが重篤)
- 極端な脱水や重い腎機能障害があるときに発生の可能性
- 強い倦怠感、呼吸の乱れ、吐き気、意識障害など
- 水分制限中・腎障害・脱水がある方は医師と相談
現在では用量や適応がしっかり管理されており、重篤な副作用は極めてまれになっています。
腎機能とメトホルミン
かつては「腎機能が悪いと使えない」とされていたメトホルミンですが、近年はeGFR(腎機能の指標)に応じた適切な用量調整が可能になっており、eGFRが30以上あれば慎重に使用可能とされています。
定期的な腎機能のモニタリングを行いながら、安全性を担保しつつ継続することが可能です。
当院での処方方針
当クリニックでは、以下のような方針でメトホルミンを活用しています。
- 糖尿病初期の第一選択薬として(単剤処方)
- 他の薬で効果不十分なときの併用療法として
- 肥満・高脂血症などを伴う患者様に
- 血糖値と体重、脂質まで一括でアプローチしたい方に
また、副作用に配慮し少量から開始して数週かけて増量する個別設計を行っています。
まずはご相談ください
メトホルミンは、糖尿病治療において基本ともいえる存在です。血糖値だけでなく、代謝全体を改善していく長期的なサポーターとして、今後も重要な役割を果たす薬です。
「まだ薬に頼りたくない」という方でも、メトホルミンでの早期介入により、将来的なインスリン治療や合併症のリスクを大きく下げることができます。