この記事を書いた人
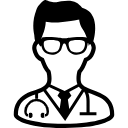
日本糖尿病学会専門医、日本内科学会認定医の資格を持ち、医師として約18年医療現場に立つ。
特に糖尿病の分野に力をいれており、糖尿病、高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症などの慢性代謝疾患の診療を得意としている。2026年5月に美濃加茂市でクリニックを開業予定。
空腹時血糖(fasting plasma glucose)は、前日の夕食後から10~12時間以上絶食した状態で測る血糖値のことを指します。一般的には、夜間に食事の影響が消えた早朝の血糖値を表し、糖尿病の診断・管理において最も基本的かつ重要な指標です。
目次
なぜ空腹時血糖が重要なのか?
血糖値は食事後に上昇をしますが、その後インスリンの作用によって適正な水準まで下がるようにできています。
一日の中で食事の影響を受けない時間帯の血糖値をコントロールすることが大切なため、空腹時血糖が指標として用いられています。
基礎的な血糖状態を反映
食後の影響がなく、肝臓からの糖放出とインスリンの基礎分泌バランスがわかります。
糖尿病診断の要件
日本糖尿病学会ガイドラインでは、空腹時血糖126mg/dL以上が2回以上確認されると糖尿病と診断されます。
治療効果の評価
食事療法や運動療法、薬物療法の効果を評価する際のベースラインとして活用されます。
一方で、近年では食事後の急激な血糖値上昇も病気のリスクを高めるとして注目されています。
詳細は血糖値スパイクをご覧ください(リンク)
判定基準(日本国内基準)
| 空腹時血糖(mg/dL) | 判定 |
| ~99 | 正常 |
| 100~109 | 正常高値 |
| 110〜125 | 境界型(糖尿病予備群) |
| ≧126 | 糖尿病の疑い(再検査要) |
※ 他の指標(HbA1c、75gOGTTなど)とあわせて総合的に判断します。
空腹時血糖が高値になる主な原因
空腹時にも関わらず血糖値が高くなる原因はいくつか考えられます。
肝臓での糖新生過剰
インスリンの働きが悪くなり、肝臓が必要以上に糖を産生・放出している状態です。
インスリンの分泌不足
膵β細胞の機能が低下することで、絶食状態でも十分なインスリンが供給されません。
暁現象(Dawn phenomenon)
早朝に成長ホルモンやコルチゾールなど血糖上昇ホルモンが分泌される生理現象。
生活習慣の乱れ
夜遅い食事、間食、寝不足、ストレスなどがホルモンバランスを乱します。
日常でできる予防・改善策
食事の工夫
- 日本人は炭水化物量や脂質の摂取量が多く、タンパク質の摂取が少なめです。タンパク質、脂質、炭水化物の摂取バランスを見直すことが大切です。
- 野菜→たんぱく質→炭水化物と、炭水化物を最後に食べることで血糖値の変化を緩やかにすることができます。
運動習慣の導入
- 朝の散歩や軽いストレッチで糖の消費量を増やすことができます。
- 週150分程度の有酸素運動でインスリン感受性を向上することができます。
- 筋トレで筋肉がつくことで筋肉内に糖を取り込める量を増やすことができます。
睡眠とストレス管理
- 睡眠は有効なストレス解消方法です。7時間前後の睡眠を確保することで自律神経を安定させることができます。
- リラックスできる時間の確保をすることで血糖値の変動を抑えることができます。
定期的な検査
・健診の結果だけでなく、セルフモニタリング(SMBG)で早期異常をキャッチすることが大切です。
空腹時血糖の測定時の注意点
正確に空腹時血糖を測るためには注意が必要です。
- 前日の夜9時以降は食事・間食を避けましょう
- 寝る前の水分は控えめに、起床後の採血直前は白湯や水を少量摂取するに留めましょう
- 検査前日の過度な飲酒、降圧薬やステロイドなどは結果に影響するため、事前に医師にご相談ください
空腹時血糖で異常値が出た方はご相談ください
当クリニックでは、空腹時血糖に加え、HbA1c、食後血糖、体重、ライフスタイルを総合的に評価し、オーダーメイドの改善プランを提供します。健康診断で「正常」と言われた方も、お気軽にご相談ください。